「松竹梅」という言葉を耳にしたことがあると言う方は多いと思います。
日本国内ではむしろ聞いたことがないという方の方が少ないでしょう。
各種お祝い事の度に現れる松竹梅。
時には飲食店のメニューにも現れる松竹梅。

松竹梅…一体何者なんだ?
ということで、今回は松竹梅という言葉の意味やその由来、
松安っぽく竹や梅に秘められたいみなどなど、
松竹梅についての雑学をご紹介していきたいと思います。
松竹梅という言葉の意味とは?

まずは松竹梅とは一体どんな意味なのか?調べてみることにしましょう。
松竹梅とは読んで字のごとく、
・松
・竹
・梅
これらをモチーフとした言葉で、これらの植物はそれぞれおめでたい意味を持っています。
そのため、松竹梅という言葉は慶事(おめでたい、よろこばしい事)や
吉祥(幸福や繁栄などを意味する言葉)の代名詞と使われ、
お祝い事の飾りつけやお祝いの品の意匠などによく使われます。
松竹梅、それぞれが持つおめでたい意味は何?
松竹梅、それぞれの植物はおめでたい意味を持っているとご紹介しましたが、
ではそれぞれの植物にはどんな意味があるのでしょうか?
一つ一つご紹介していきます。
松

まずは松竹梅の先頭を飾る松の意味を見てみましょう。
松が持つおめでたい意味はなんと「長寿」や「不老不死」!
松はほとんどの植物が枯れてしまうような冬でも緑を保っているので、
その様子がいつまでも元気な様と捉えられて長寿や不老不死のシンボルとなりました。
ちなみに、そんな松の木の寿命は一体どれくらいなのか?言うと、
なんと平均寿命2500歳、最大寿命5000歳なんだそうです。
我々人間からしてみると、0を一つ減らしても倍以上の寿命を持っています。
そりゃ長寿や不老不死のシンボルになるわな。
また、松は昔から「神の天降り(あまくだり)を待つ木」と言われており、
神聖なイメージがあるのもおめでたい要素の一つと言えます。










平均寿命2500年とか俺の寿命の何倍やねん…。









ちなみにアザラシの寿命は大体30年くらいらしいぞ。










松に比べれば俺達アザラシの寿命なんて一瞬みたいなもんなんだなぁ…。
竹

次は松竹梅の二番打者である竹についてです。
竹のおめでたい要素の一つは、まずは松と同じく冬になっても枯れずに緑を保ち続けている生命力です。
また竹にはもう一つおめでたい要素があります。それは竹は繁殖力の強さです。
竹はおよそ20m前後の高さまで成長しますが、
その高さに成長するまでに有する時間はなんとたったの50~60日ほど!
ピーク時には1日に1m以上も伸びたと言う記録もあります。
また、竹には地下茎というのが存在し、
この地下茎からまた新しい竹が生えてくるのですが、
この地下茎も1年になんと8mも広がるそうです。
あまりにも成長力・繁殖力が強く、竹が広がり過ぎたせいで
他の農作物などの成長が阻害されてしまう竹害というのも起こりますが、
竹はこうした性質から繁栄の象徴として松竹梅の一角に名を連ねています。
また、日本には古くから
「空洞なものには神様が宿っている」
という言い伝えがあるそうです。
竹の中も空洞になっているので、
そうした理由もあっておめでたい植物の象徴になったのかもしれませんね。










もし俺の身長が1日で1mも伸びたら母ちゃんもビックリするだろうな。









母ちゃんだけじゃなくてお前の関係者全員がビビるわ。










それはそうと、何かお腹が空洞になってきた気がするから、今俺のお腹に神様が宿ってるかもしれない









お前のお腹にはすぐに神様が宿るからなぁ。
梅
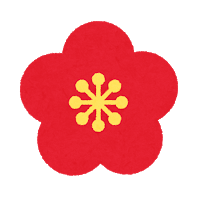
松竹梅の最後を飾る梅。
梅はどんなおめでたい意味をもっているのか?と言うと、
長寿や気高さ、そして繁栄の象徴として扱われているようです。
梅の寿命は何百年単位と言われており、
松ほどではありませんが十分長い寿命を持っています。
そして、梅は老齢に差し掛かっても春になると
鮮やかな花を元気に咲かせてくれます。
その寄る年波にも負けないという様子は
気高さを表していると言えるでしょう。
また、梅が繁栄の象徴とされているのは、
毎年春になると他の植物に先駆けて美しい花を咲かせるから…
というのが理由だそうです。
また、他の説としては「梅」という漢字の
「毎」の部分が「母」に似ているから…などという説もあります。
日本人の大好きな縁起の良い系ダジャレって感じですね。









俺も過酷な環境の砂漠で力強く生きてるから、強さの象徴として仲間に入れてくれねーかな。松竹梅サボみたいな感じで。










強さの象徴枠だったら、寒い北国でたくましく生きてる俺がいるから諦めるんだな。









植物ですらないだろ。
松竹梅の由来

おめでたい言葉の代名詞として存在する松竹梅ですが、
その元々の由来は「歳寒三友」と言われています。
歳寒三友とは中国の文人画の画題の一つで、
「冬に友とすべき三つのもの」という意味を持っています。
この歳寒三友というテーマで書かれた絵の中には、
冬でも元気に緑を保つ松と竹、
そして冬の終わりと春の到来を知らせるように花を咲かせる
梅が一緒になった絵が多かったそうです。
そのため、この三つの植物はいつしかワンセットとして認識され、
それが日本に渡って来たそうです。










俺達もそのうちワンセットにまとめられるかもしれないな。









ないだろ。
また、松竹梅は元々は日本でも単なる絵のテーマの一つでしたが、
まず松が平安時代(794~1185年)に長寿の象徴とされ、
次に竹が室町時代(1336~1573年)に繁栄の象徴に、
最後に梅が江戸時代(1603~1868年)に気高さや長寿の象徴となり、
松竹梅=めでたいという認識に変わっていったそうです。
松竹梅の順位はどれが上?
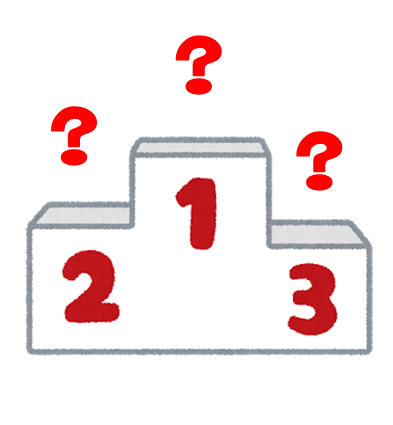










格闘漫画とかでは違う格闘技同士が出会うと『どっちがつええんだ!?』ってなるけど、松竹梅の三人は一体どういう力関係なんだろ?









俺のいないところでNo.1争いするなよ。
ちょっと立派なお寿司屋さんや料亭などの飲食店では、
料理のコースのランクを松竹梅で表現する場合もよく見られますよね。
ここで気になるのが
「松と竹と梅、一体誰が一番上で、誰が一番下なんだ!?」
という点です。
しかし、これはお店によっては一番最初に来る松が一番豪華!という場合もあれば、
いやいや一番最後に来る梅が一番豪華!というパターンもあります。
つまり、お店の表記の仕方の問題であって、
どれが一番上でどれが一番下かというのは明確には決まっていません。










でも、何だかそう考えると竹って1位になれるパターンなくて残念だな。









口が過ぎるぞ。竹さんは一番より二番の男だからいいんだよ。常に一定して2位になるのって逆にすごいと思わんか?
また、これも雑学ですが、商品のランクを
・特上
・上
・並
ではなく松竹梅で表現するのは、
その方が何だか上品な感じがするからなんだとか。
確かに特上、上、並と言われると、
明確に商品に優劣関係が見えて
「何だか並は安っぽく見られそうで頼みづらいなぁ…」
とか色々考えてしまいそうになってしまいます。
しかし、松竹梅なら名前の上では上下関係はありませんので、
どの商品も気兼ねなく注文することが出来る気がしますね。
我々日本人は特に松竹梅のトリオを目にしたり耳にしたりする機会が多いですが、
一つ一つ意味を調べてみると中々興味深いストーリーがあって面白いですね!
それでは、今回はこの辺で終わり!
